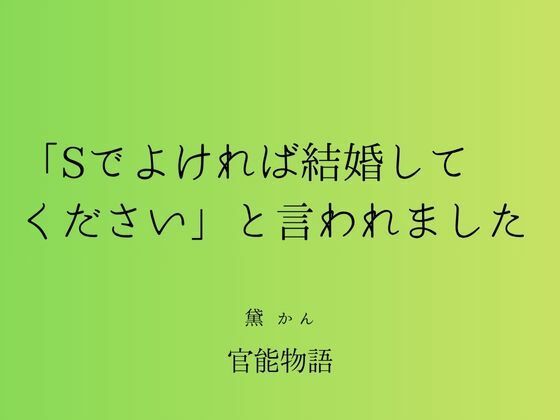
31歳の真希は、4年間交際した彼氏・修司から突然の別れを告げられる。「エッチの相性が悪い」という衝撃的な理由に、真希は女としての自信を打ち砕かれる。傷心の真希は、実家で家族からの結婚プレッシャーにうんざりしながらも、やむなく婚活に目を向ける。
そんな中、真希は同じく恋人との別れを経験したばかりの男性、恭司と出会う。恭司もまた、恋人から「Sな性癖についていけない」と振られた過去を持っていた。互いの奇妙な共通点に興味を抱いた二人は、試しに恭司のSな「責め」を真希が受けてみることにする。
すると、真希の身体はそれまで知らなかった感覚に目覚める。恭司のリードは、真希の中に眠っていた「女としての喜び」を呼び覚まし、初めて心から満たされる体験をするのだった。この出会いをきっかけに、真希と恭司は結婚を前提とした交際をスタートさせる。
物語は、恭司のちょっと意地悪で、時に甘美な「責め」によって、真希が未体験の快楽と悦びに溺れていく日々を描く。二人の間に育まれる絆と、互いの秘めたる欲望が織りなす、大人のラブストーリー。これは、傷つけられた過去を乗り越え、自分だけの「本当の愛と快楽」を見つける女性の物語。
総字数 約85,000字(読了時間 約2時間50分)
〈冒頭4000字〉
6月下旬、蒸し暑い日曜の夜だった。真希は一瞬、修司の言葉が理解できなかった。いや、言葉そのものの意味は分かったが、その言葉が発せられた意図が全くつかめなかったのだ。
「おれたちさ、やっぱり、別れよう」
真希の薄暗い寝室で、二人が横たわるセミダブルのベッドの上で、その言葉は発せられた。真希の視界には、4年間という歳月を共にした彼氏、修司がいた。彼は現在35歳。真希が27歳の時から付き合い始め、これまで穏やかな関係を築き、お互いに結婚も視野に入れていたはずだった。今日も、都心の商業施設で映画を見たり、新しいカフェで流行りのスイーツを試したりと、ごくありふれた、それでいて心温まるデートを楽しんだばかりだった。そして、真希の部屋に戻り、つい先ほど、二人の愛を確かめ合ったばかりだったのだ。
「え、な、なんで?」
真希から漏れたのは、それ以外の言葉が見つからなかったからだ。なぜ、このタイミングで別れを告げられなければならないのか。冗談なのだろうか、と一瞬思ったが、修司の真剣な眼差しは、それが決して笑えない冗談ではないことを物語っていた。彼の瞳の奥には、冗談では済まされない重い決意のようなものが宿っているように見えた。
彼はゆっくりと上体を起こした。その動きに釣られるように、真希も体を起こすと、修司は沈んだ声で言った。
「ずっと我慢しようと思ってたんだけど、やっぱり無理だって思ってさ」
何のことだろうか、と真希の頭の中は疑問符でいっぱいになった。我慢? 何を?
「真希は本当にいい子だと思うよ」
それは、決まって別れ話の前に聞く、聞き飽きた前置きだった。この後に続く、どんな「素敵な」本論が待っているのかと身構えていると、修司は意外な言葉を口にした。
「でもさ、真希としても全然よくないんだよ、エッチが」
「えっ」と、真希は予想外の言葉に、別の意味で驚きを隠せなかった。まさか、そんな理由だったとは。
「真希ってずっと受け身で、全然セックスを楽しんでないじゃん? おれ、それでもいいと思ってたんだけど、やっぱりこれって大事なことなんだよな」
彼は一人で納得するように、何度も頷いた。真希は呆然とした。
「ちょ、ちょっと待って、わたしは、修司とするとすごく幸せな気分になって、それで、ずっと修司も同じだと思ってた」
震える声で真希は訴えた。
「悪いけど、それは、おれがこれまで演技してたんだよ。おれは、真希の人柄が好きだから、エッチは二人の関係にとって、二の次三の次だと思ってたんだ。でも――」
彼は首を横に振った。全てを諦めたかのような、諦観の表情がそこにはあった。
「待って待って、よく話し合おうよ。それならそれで、これから修司が気持ち良くなるように、わたし努力するから」
真希はすがるように、修司に少し体を寄せた。彼のぬくもりを感じると、まだやり直せるのではないかという淡い期待が胸に灯る。
「悪いけど……今抱いてみて分かった。おれ、もう真希を抱く気になれないんだ」
修司は、突き放すような、まるで最後通牒のような言葉を口にした。真希の心臓が冷たくなった。
「え……?」
「今だってイッてないし」
彼は射精していなかった、というのだ。真希は、心から申し訳ない気持ちになった。自分のせいで、彼を満足させられなかったという事実に、胸が締め付けられる。
「ご、ごめん」
「こういうのは謝ることじゃないのかもしれないな。ただ、おれたちが合わないってだけかもしれないからさ」
修司は「ふうっ」と長い溜息をついてから言った。そして、ゆっくりとベッドから降りた。真希は反射的に彼の腕を掴んだ。
「お願い、修司。考え直して。わたし、変わるから」
真希は懇願するように修司の手に自分の手を重ねたが、彼は真希の手にそっと自分の手を重ねると、静かにそれを払うようにして言った。
「真希にはもっと真希に尽くしてくれるような人が似合うよ」
その言葉を最後に、彼は速やかに着替えを終え、真希の部屋から出て行った。真希は一人残され、裸のまま、しばらくベッドの上で呆然としていた。部屋には、まだ修司の残り香が微かに漂っていたが、それも時間とともに薄れていくような気がした。窓の外は、すでに宵闇に包まれ、夏の虫の声が静かに響いていた。真希の目から、一筋の涙が頬を伝って流れた。
〇
三日後、まだ修司との別れから立ち直れていない真希は、実家で夕食時に軽い気持ちでそのことを話した。すると、4歳年下の妹が、フォークを落とすほどの素っ頓狂な声を上げた。
「ええっ! お姉ちゃん、別れちゃったの!?」
妹の瞳は大きく見開かれ、信じられないといった表情をしている。ちゃぶ台の上には、母が作った肉じゃがの甘い香りが漂っているが、真希の心はそれに全く反応しない。
「修司さん、いい人だったのに、どうして?」
「いや、まあ、その……なんだろう、性格の不一致ってやつかな」
まさか、性の相性が悪くて振られたなどとは口が裂けても言えず、真希はありきたりな言葉で誤魔化した。
「性格の不一致って……子どもじゃないんだから、不一致だったら、合わせる努力をしないと!」
ちゃぶ台をひっくり返さんばかりの勢いで、妹が立ち上がった。真希は、なぜ妹がそこまで自分の恋愛に気を揉むのか、これが姉妹愛というものか、とホロリとしそうになったその時、妹は信じられない言葉を吐いた。
「お姉ちゃんが先に結婚してくれないと、わたしがしづらいじゃん」
まったく自分に引きつけた話だったので、真希は心の中で「感動を返せ」とクレームつけた。
「そんなの時代遅れでしょ。わたしに構わず、さっさとすれば?」
「そういうわけには行かないんだって!」
「行かないったって、あんただって若くないんだし」
「お姉ちゃんに言われたくないよ」
そりゃそうだ、と真希は素直に認めたが、もう別れてしまったものはどうしようもない。
「婚活でもしようかな」
思いつきでそう口にすると、リビングの奥から、父の咳払いが聞こえてきた。
「別にしたくないならしなくてもいいんだ」
父の声には、娘を心配する親心が滲み出ている。
「お父さんは黙ってて。しなくていいわけないでしょ」
妹がすぐに父に反論した。
「そうですよ」
台所から戻ってきた母も、妹に加勢する。
「誰でもいいというわけにはいかないけど、誰かいい人がいたら、次は逃がさないようにしないと」
次と言われても、ついこの前別れたばかりだ。次のことなんて考えられないし、そもそもすぐに次があるかどうかなんて分からない。真希の頭の中は、まだ修司との別れでいっぱいだった。
「そんなこと言ってる場合じゃないでしょ! 婚活するっていうなら、明日にでも結婚相談所に行きなよっ」
妹のぐいぐいとした勢いに負けた格好で、真希は「はい」と力なく答えた。真希の心は、まだ修司の影から抜け出せずにいたが、家族の期待という名の重圧が、否応なしに真希を未来へと押し進めようとしていた。
〇
とはいえ、翌日は仕事があったため、真希が結婚相談所へ足を運んだのは、翌週の土曜日だった。結婚相談所という場所は、考えてみれば当たり前だが、土日こそが稼ぎ時とばかりに開いているものだ。初めて訪れるその場所は、想像していたよりもずっと洒落たオフィスで、真希は少しだけ緊張しながら自動ドアをくぐった。
妹の言葉に背中を押され、そして自分で口にしたことではあるが、真希の心の中に「婚活をしよう」という気持ちが100%あったかというと、そうでは全くない。ただ男と別れてしまった今、他に特別することもなかった。暇つぶしが実益を兼ねるなら、それは良いことだろう、くらいの軽い気持ちだったのだ。
「本当に結婚したいとお考えですか?」
相談を開始してまだ5分も経たないうちに、40代前半と思しき女性相談員に、その核心をズバリと突かれた。真希は内心ドキリとしながらも、反射的に「は、はい」と頷いた。ここで否定すれば、目の前の相談員の立場がないだろうと思ったからだ。彼女はじろりと疑り深い目を真希に向けてきた。真希は内心で「ひいっ」と小さく悲鳴を上げた。まるで心の奥底を見透かされているような気がした。しかし、相談員はそれ以上追及することなく、口元に微かな笑みを浮かべた。
「でしたら、もっと具体的にご希望を話していただいた方がいいですね」
そう言いながら、彼女は手元のタブレットに視線を落とした。そして、職業、年収、結婚経験の有無、健康状態、性格、趣味、家族構成、そして容姿に至るまで、ありとあらゆる項目について希望を述べるように真希に促した。真希は一つ一つの質問に答えながら、しかし内心では「こんなに希望通りの人がいるなら、その人はとっくに結婚しているのではないだろうか」と思った。まるで完璧な人間像を描いているようで、現実離れしていると感じたのだ。
「これはあくまで希望をお聞きしているだけですので、そこから妥協点を見出していくわけです」
「妥協」と来た。結婚というのは、妥協してするものなのだろうか。その疑問が真希の顔に出ていたのだろう、相談員はにこやかに、しかしきっぱりとした口調で説明してくれた。
「結婚生活自体が妥協の連続なのです。ですから、お相手の条件という点で妥協するのはある意味で当然のことでしょう」
その論理的な説明に、真希は「なるほど」と納得せざるを得なかった。同時に、この相談員自身はどのような人と結婚し、どのような結婚生活を送っているのだろうか、とふと思った。他人の相談に乗るくらいなのだから、さぞかし素晴らしい結婚生活を送っているに違いない、と勝手な想像を巡らせた。
真希がそんなことを考えているうちに、相談員はカタカタとリズミカルにキーボードをタッチし、パソコン内にある膨大なデータを照合し始めた。数分後、真希のために三人の男性候補をリストアップしてくれた。もちろん、真希の希望全てを叶える人物ではないが、「希望にできるだけ近い人たち」だという。
「この三人のうちのどなたかとお会いになるのはいかがですか?」
彼女の言葉に、真希は「できることなら全員に会いたい」と即答した。いわゆる「保険をかける」つもりだった。一人に絞って失敗するよりも、複数に会ってから判断したい。
「分かりました。では、初めはどなたがよろしいでしょうか?」
真希は迷わず、リストの一番上にあった「年収が最も高い人」を選んだ。
「Sでよければ結婚してください」と言われました
 マンガ
マンガ



